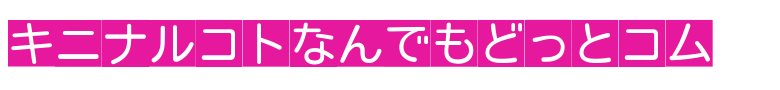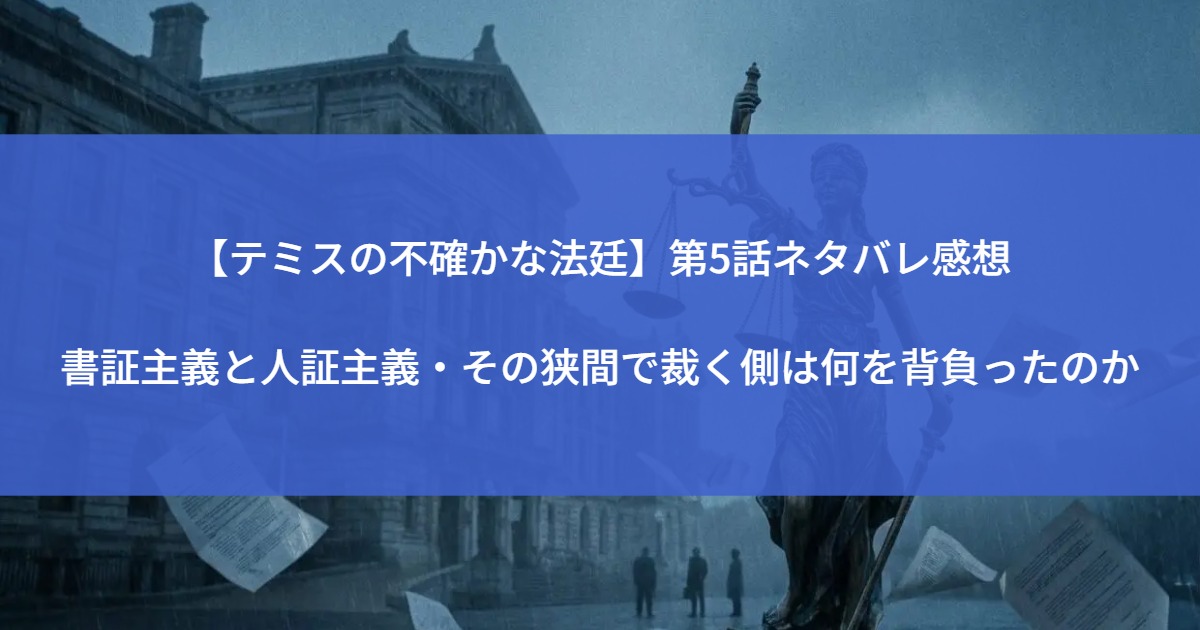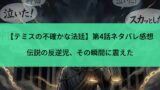NHKドラマ10『テミスの不確かな法廷』、2月3日に放送された第5話を視聴しましたか?
これまでのリーガルサスペンスとしての面白さに加え、今回は胸が締め付けられるような社会のリアリティが描かれ、見終わった後に深く考えさせられる回でしたね。
今回は、第5話「書証主義と人証主義」のあらすじを振り返りつつ、ドラマが私たちに問いかけた「裁くことの重さ」についてじっくり紐解いていきたいと思います。
『テミスの不確かな法廷』第5話が「重い」と感じた理由
※ここからは第5話のネタバレを含みます。未視聴の方はご注意ください。
放送終了後、SNSではこれまでの回とは少し違う空気が流れていました。
「面白い」という興奮よりも、「泣いた」「しんどい」「深く刺さった」といった、切実な感情を吐露する声が多く見られました。
なぜ、今回の第5話はこれほどまでに視聴者の心を揺さぶり、そして「重い」と感じさせたのでしょうか。
それはやはり、ドラマの中で描かれた事件が、決してフィクションの中だけの出来事とは思えない「痛み」を伴っていたからではないでしょうか。
これまでのエピソードでも法廷ドラマとしてのスリルはありましたが、今回は私たちの住む社会の足元に横たわっている問題――ヤングケアラーや無国籍児童、外国人労働者が置かれた環境など――が、事件の背景に色濃く映し出されていました。
特に、ドラマを見ている私たちが普段生活している中では見えにくい、あるいは無意識に見ないようにしてしまっている「社会の隙間」にスポットライトが当てられたことで、単なる謎解きの楽しさ以上に、現実に突きつけられるような苦しさを感じた方が多かったのだと思います。
「正義とは何か」という問いは、このドラマの根底に流れるテーマですが、今回はその正義が、立場の弱い人たちにとってはあまりに遠く、冷たいものであるという現実が描かれていました。
それを見て、「救われてほしい」と願う気持ちと、「どうにもできないのか」という無力感が入り混じり、結果として「重い」という感想につながったのだと感じます。
この「重さ」こそが、制作陣が私たちに伝えたかったメッセージの一つなのかもしれません。
第5話あらすじ整理|刺傷事件から社会の闇へ
物語は、ショッキングな事件から幕を開けました。
強制執行の現場に向かった執行官の津村綾乃さんが、何者かに刺されるという事態が発生します。
いつも冷静で、淡々と職務を全うしてきた津村さんが襲われるシーンには、息を呑んだ方も多かったのではないでしょうか。
この刺傷事件をきっかけに、物語は「誰が刺したのか」という犯人探しから、その背後にある「なぜ刺さなければならなかったのか」という悲しい背景へと深く潜っていきます。
強制立ち退きを命じられたアパートの一室。
そこには、表向きの書類には記されていない生活の痕跡がありました。
捜査が進むにつれて浮かび上がってきたのは、ある少女の存在です。
彼女は日本で生まれ育ちながらも、法的な身分を持たない「無国籍」の状態に置かれていました。
学校に通うことも、病院で適切な治療を受けることもままならない少女。
そして、そんな彼女を支えようとしていたベトナム人のグエンさんたちの存在。

ドラマは、津村さんが刺されたという「事件」の奥に、制度の狭間で息を潜めて生きるしかない人々の「生活」があったことを丁寧に描き出していきます。
「生きることを諦めない」というメッセージが込められたラムネのエピソードや、少女が大切にしていたペンダントの謎。
これらが一つひとつ繋がっていく過程は、ミステリーとしての面白さを保ちつつも、その真相に近づくほどに胸が苦しくなる構成でした。
単純な「善と悪」では割り切れない構造が、今回のあらすじの核心です。
法に従って立ち退きを迫る側と、法に守られず居場所を失う側。
その衝突が、暴力という悲しい形で噴出してしまったこと。
そして、その引き金を引いたのが誰であれ、そこに至るまでの過程に社会の歪みが横たわっていることを、この第5話は静かに、しかし強烈に突きつけてきました。
「書証主義 vs 人証主義」が突きつけた司法の苦しさ
今回のサブタイトルにもなっている「書証主義」と「人証主義」。
法律用語のようで少し難しく感じるかもしれませんが、ドラマの中では非常にわかりやすく、かつ残酷な対比として描かれていましたね。
「書証主義」とは、文字通り「書類(書証)」を重視して判断すること。
契約書や公的な記録など、形に残る証拠を最優先にする考え方です。

これは司法の安定性を守る上で非常に強力な武器です。
書類さえ整っていれば、誰が見ても同じ結論が出せる。
「確かさ」を担保する上では欠かせない要素です。
しかし、今回のドラマでは、その「強さ」が同時に「冷たさ」としても描かれました。
書類に名前がない人間は、そこに存在しないのと同じなのか。
紙切れ一枚で証明できない事情は、考慮に値しないのか。
書類というフィルターを通すことで、そこにあるはずの体温や叫びが切り捨てられてしまう危うさが浮き彫りになりました。
対する「人証主義」は、人の証言や言葉(人証)を重視する考え方です。
書類には書けない真実、人の心の機微、その場の空気感など、生の情報を拾い上げることができる点に「希望」があります。
安堂さんがこだわったのも、まさにこの部分でした。
書類だけでは見えてこない、少女たちの本当の姿を見ようとする姿勢です。
しかし、人の言葉は変わります。
嘘をつくこともあれば、記憶が曖昧なこともある。
ドラマ内でも、証言に頼ることの「危うさ」や、感情に流されることで事実を見誤るリスクについても触れられていました。
第5話の法廷シーンや議論の中で、この二つの主義が激しくぶつかり合いました。
どちらが正しい、と安易に答えを出さないところがこの作品の誠実さだと感じます。
書類を重んじなければ法的な秩序は保てない。
けれど、人の声を聞かなければこぼれ落ちてしまう命がある。
このジレンマこそが、タイトルにある「テミスの不確かな法廷」という言葉の意味を、より一層深くしていたように思います。
落合・津村・安堂が背負ったもの
第5話では、主要キャラクターそれぞれが、自身の立場と人間としての感情の間で揺れ動く姿が印象的でした。
まずは、裁判官である落合知佳さん。
彼女はこれまで、法の番人として「ルール」や「書類」を重んじる立場を崩しませんでした。
しかし、今回はその信念が揺らぐ瞬間が何度も見られました。
法廷という「箱の中」で書類を見つめるだけで、本当に人を裁けるのか。
彼女がふと漏らした「ガラスの天井」という言葉には、組織の中で自身の理想と現実の壁にぶつかっている苦悩が滲んでいました。
目の前の少女の境遇を知り、心が動きそうになる自分と、裁判官として公平であらねばならない自分。
その葛藤を目線の動きやわずかな表情の変化で演じきった恒松祐里さんの演技は、見ているこちらの胸を締め付けるものがありました。
そして、執行官の津村綾乃さん。
彼女は「執行官」という、ある種もっとも現場で矢面に立つ仕事をしています。
淡々と職務をこなしているように見えますが、今回彼女が刺されたことは、その仕事が常に人の恨みや絶望と隣り合わせであることを残酷なまでに証明してしまいました。
それでも彼女は、被害者でありながら、加害者側の事情に対してもある種の理解を示そうとする強さを持っていました。
市川実日子さんが演じる津村さんの、多くを語らないけれど芯のある佇まいが、この悲劇に一本の筋を通していたように感じます。
最後に、主人公の安堂清春さん。
松山ケンイチさん演じる安堂さんは、今回も「わからないことをわかっていないと」というスタンスで、徹底的に事実に迫ろうとしました。
彼は、書類にも証言にも完全な信頼を置かず、ただ「そこにいる人間」を見ようと足掻いていたように見えます。
書証主義の壁にぶつかりながらも、人証主義の危うさも理解している。
その上で、どうすれば目の前の依頼人や、関わってしまった人たちを救えるのか。
弁護士として、あるいは一人の人間として、彼が背負っているものの大きさが、安堂さんの背中から伝わってくるようでした。
三者三様の「正義」と「職務」があり、誰も間違っていないからこそ、誰かが傷ついてしまう。
そんなやるせない構造の中で、彼らが見せた人間臭い揺らぎこそが、このドラマの最大の魅力なのかもしれません。
第6話へ続く違和感と期待
物語のラストには、シリーズ全体の謎に関わる「前橋一家殺人事件」や、安堂さんのお父さんに関する話題も少し触れられましたね。
今回の重いエピソードを経たことで、安堂さんが追い求めている過去の真実が、より一層深い闇の中にあるように感じられます。
さて、ここで視聴者にとって一番の試練が待っています。
次回は冬季オリンピックの中継が入るため、なんと2週間の放送休止となります。
SNSでも「ここで2週空くのは辛い」「3週間後まで待てない」という悲鳴にも似た声が溢れていました。
私もまったく同じ気持ちです。
しかし、この空白の期間は、今回描かれた重厚なテーマを自分なりに消化し、安堂さんたちが次にどう動くのかを予想する良い時間になるかもしれません。
落合さんは今回の経験を経て変わっていくのか。
安堂さんの過去はどう繋がってくるのか。
第6話での再会を楽しみに、今は余韻に浸りたいと思います。
参考・出典
- ドラマ公式サイト
- キャスト・登場人物
- 原作
『テミスの不確かな法廷』の見逃し配信はコチラ!